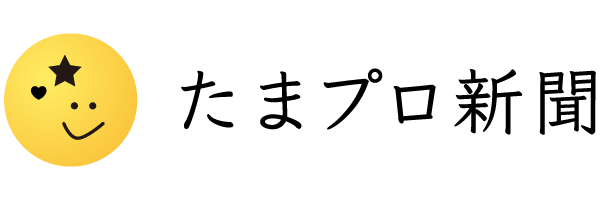住宅のリースバック契約をして、その家賃ほんとに払い続けられますか?
- 住宅のリースバック契約
- 主に事業者が個人から自宅(マンション、戸建て住宅)を購入し、その個人(売主)に貸し付けることを併せた契約のことです。
個人(消費者)が十分納得して契約をしているケースもある一方で、自宅に無断で訪問し、冷静に判断できない状況や高齢者の判断力低下につけ込んで、安い値段で買い叩くというケースもあります。

住み続けられないケースも
「売却後もそのまま住み続けられる」と説明されたが、契約後に家賃が大幅に値上げされ支払えなくなった・・・
そんな深刻な被害もある住宅のリースバック契約について、弁護士に聞いてみました!
被害を未然に防ぐために
- 不動産の買取の場合、特定商取引法上のクーリング・オフ等が適用されないので、安易に契約をしないこと。
- 実印・印鑑証明は、本人の同意の上で、家族と話合いをしないと持ち出せないようしておくこと。
- 債務整理のためのリースバックは、売り急ぐ形になり、安く買い叩かれてしまうので、他の手段(破産、民事再生、任意整理など)を検討すること。
契約済みでも諦めないで!
リースバック契約を結んでしまったとしても、例えば、次のような対応により、被害を抑えられる可能性が考えられます。
諦めずに消費生活相談窓口や弁護士に相談してみましょう。
- 登記変更前ならば
- 消費者契約法の取消権、民法の取消権を根拠に登記を移すことを拒絶するか検討する。
- 紛争が解決するまで登記に必要な書類(印鑑証明書や実印)を事業者に渡さない。
- 予備的に手付解除をすることも検討する。
- 登記変更後ならば
- 消費者契約法・民法に基づく取消を主張することになる。
第三者に売却がされると、救済がより困難になるので、処分禁止の仮処分(勝訴したときは登記が戻せるようにする手続)を検討する。 - 安い値段で売却させられている場合には、時価との差額について民法の不法行為に基づく損害賠償を求めることを検討する。
- 消費者契約法・民法に基づく取消を主張することになる。
今回の情報は、神奈川県と神奈川県弁護士会との「SDGs推進協定」の一環で、神奈川県弁護士会の協力により 作成したものです。「誰ひとり取り残さない」社会の実現に向け、消費者被害対策等について両者が連携して 取り組んでいくこととしています。
消費生活相談は・・・
消費者ホットライン:局番なし188(身近な消費生活相談窓口につながります)
弁護士に相談したい方は・・・
神奈川県弁護士会 消費者被害相談:予約受付 045-211-7700
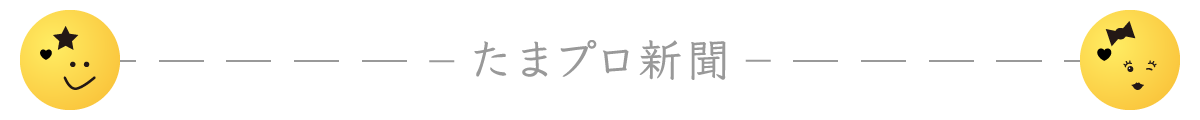
この記事は、神奈川県くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 発行『かながわ消費生活注意・警戒情報163号』を元に作成しています。
なお、画像は「挿絵」として掲載しているもので、本文とは関係ありません。
神奈川県 公式サイト『かながわ消費生活注意・警戒情報』の情報は、ご自由にコピー、回覧していただき、消費者被害の未然防止にお役立てください。PDFファイルもあります。